
公開日:
インバウンド宿泊体験の“多様化と深化”─2030年に向けたホスピタリティ戦略─|近鉄・都ホテルズ 能川氏・温故知新 松山氏・Nazuna 渡邊氏|GLOBALIZED インバウンド

WOVN マーケティング編集部

本記事のポイント
-
インバウンド向けも自社の発信力強化が重要。デジタルマーケティングの徹底で自社予約比率50%超も可能に
-
人と人のアナログなコミュニケーションによる信頼感の醸成も不可欠
-
地域や宿が持つ魅力や体験価値、文化をストーリーと共に伝える
Wovn Technologies株式会社は、2025年10月7日に「GLOBALIZED インバウンド」を開催し、「世界は、もっと日本を好きになる 〜AI・多言語で拓く、15兆円に向けた訪日インフラ整備〜」をテーマにセッションをお届けしました。
宿泊業界のゲスト講演では、株式会社 近鉄・都ホテルズの能川 一太 氏、株式会社温故知新の松山 知樹 氏、株式会社Nazuna の渡邊 龍一 氏を迎え、「インバウンド宿泊体験の“多様化と深化”─2030年に向けたホスピタリティ戦略─」と題して、インバウンドに向けた各社のアプローチや、宿泊体験が持つ価値の届け方についてお話しいただきました。本レポートではその内容をご紹介します。
【登壇者】
能川 一太 氏
株式会社 近鉄・都ホテルズ
取締役 ホテル運営本部 副本部長
近畿日本鉄道で、駅や美術館などの設計、建築、観光プロモーション、レジャー事業を担当。志摩スペイン村テーマパーク支配人、シェラトン都ホテル東京総支配人を経て、現在は国内のホテル事業全般を担当。
松山 知樹 氏
株式会社温故知新
代表取締役
1973年米国生まれ、大阪育ち。東京大学大学院 都市工学修士課程修了後、株式会社ボストン・コンサルティング・グループに入社。ベンチャー支援企業の創業に参画。2005年に株式会社星野リゾートに入社、2007年に同社取締役就任。その後独立し、2011年2月に株式会社温故知新を創業。東北にある旅館の復興支援のサポートを20軒ほど手掛けた後、2015年に愛媛県松山市に初の運営施設「瀬戸内リトリート 青凪」を開業。現在11ホテル、4つのレストランを運営。
渡邊 龍一 氏
株式会社Nazuna
代表取締役
2016年にコロンビア・ワークス株式会社に入社し、不動産営業と開発を経験。その後、人事部で採用や組織醸成を担当し、BnA Alter Museumの支配人に。2021年に Nazuna に参画し、2023年に取締役、2024年4月から代表取締役に就任。2026年「宿泊業界の革命児」になることを目指し、新たな取り組みを推進中。
|
目次 |
WOVN:
本日は事業展開の異なる3社をお招きし、どのような体験を提供し、どのように「選ばれる宿」をつくるのかを軸に、インバウンドへの効果的なアプローチ方法について、お話を伺います。まずは自己紹介をお願いします。
能川(近鉄・都ホテルズ):
当社は、複数ブランドを展開しています。食事を含むフルサービスを提供する「都ホテル」、アクセスなどの利便性が高い宿泊特化型の「都シティ」、志摩地域にあるリゾート型の「都リゾート」。USJ のオフィシャルホテルや旅館も運営しています。
マリオット・インターナショナルと提携し、「都」「マリオット」両ブランドを持つホテルもあるため、北米からの集客が多いのが特徴です。さらに、アメリカには大谷翔平さんの壁画で度々露出する「都ホテル ロサンゼルス」があります。現地でのブランド認知が進むことで、訪日の際にも安心して選んでいただける効果があると考えています。
松山(温故知新):
当社のミッションは、「旅の目的地=デスティネーションホテル」の創出です。地方にある当社のホテルを目指して来てもらうことで、その地域に人の往来が生まれて経済も動きます。ホテル滞在と共に、その土地ならではの体験をしてもらい、地域経済の活性化に貢献したいと考えています。そのためにも、「地域のショーケース」であり、旅の目的地となるような唯一無二のホテル・旅館・レストランを、全国各地で展開しています。「日本に行く時は、温故知新の宿に泊まりたい」と指名してもらえる存在を目指しています。
渡邊(Nazuna):
当社は、京都を中心に古民家をリノベーションした旅館を運営しています。各施設には日本文化に関連するテーマを設定している点も特徴です。日本古来の良さである人の温かさを「おせっかい」と表現し、細やかなおもてなし体験の提供をポリシーにしています。
現在は、SNS 発信をはじめとしたマーケティング戦略にも力を入れています。

ホテル各社のインバウンドの現在地
WOVN:
各社のインバウンドの現状について教えてください。
能川(近鉄・都ホテルズ):
現状のインバウンド比率は半分強です。集客が多いのは都市部で、大阪が最も多く、次いで東京、博多、京都の順です。ホテルのタイプによっても比率は大きく異なります。しかし、特定の国・エリアへの依存はリスクがあるため、インバウンドに過度に偏らないバランスが重要だと考えています。
松山(温故知新):
インバウンド比率は地域や施設によって異なります。例えば、白馬のようなスキーリゾートでは、冬のスキーシーズンの外国人宿泊者比率は約95%です。一方で全国の宿泊施設全体で平均すると、15%〜20%程度です。地方の施設では、「当社のホテルがあるからこそ、外国人旅行者がその地域を訪れている」と実感する場面も少なくありません。
インバウンドは現状の約3,000万人から2030年までに6,000万人を目指す政府目標がありますし、これからも更に成長させていきたいと思っています。
渡邊(Nazuna):
当社がメインで事業を展開している京都では、インバウンド比率は約8割です。コロナ禍で成功した SNS 強化による集客施策をインバウンド向けにも応用しています。具体的には、海外のお客様は、歴史やストーリー、宿泊で得られる体験を重視しているため、それらの魅力をどう伝えるかを意識しています。なお、広告費も約8割はアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア向けであり、海外のお客様をメインターゲットにしています。
今後は京都以外の施設でもインバウンド比率を7〜8割ほどまで上げつつ、日本人のお客様のファン層も増やしていきたいです。
数値分析とデジタルマーケティングで自社予約比率50%を達成
WOVN:
インバウンドを増やしていくうえで、まずどのようにして認知を広げたのか。特に効果があったチャネルやアプローチはありますか?
渡邊(Nazuna):
SNS が発達した時代において、いかに自社の発信力を伸ばしていくかが重要だと考えています。一般的に宿泊予約は OTA がメインと言われますが、当社の場合は発信力強化の効果により、自社予約比率が約45%〜50%まで伸びており、箱根の施設では約60%に達しています。
海外の方へのリーチは、ターゲットを細かく絞ることができる、 Meta や Google、TikTok の広告などを活用しています。お客様となりえるターゲットにメッセージを届けるという点では、日本人向けでも海外向けでもあまり違いはありません。
能川(近鉄・都ホテルズ):
当社の自社予約比率は、マリオット経由を合わせてもまだ約25%ほどです。Nazuna さんに伺いたいのですが、自社予約比率を上げるための秘訣は何ですか?
渡邊(Nazuna):
デジタルマーケティングを徹底し、数字を見て分析することが不可欠です。公式サイトの分析には GA4 を使い、どこで離脱しているのか、どの客室タイプがコンバージョンにつながりにくいのか、などを細かく分析しています。写真を1枚変更するだけで、離脱率やコンバージョン率は数%、予約も何十件と変わることもあります。
また、OTA も含め全ての予約サイトにおける PV 数や予約数、そしてホテル全体の PV 数と予約数を数字で紐解いています。この分析を踏まえて、動画でのアプローチや SNS のクリエイティブの改善、OTA のキャンペーンへの参加調整などの対策を講じることで、自社予約比率が上がっていきました。

(Nazuna 渡邊 氏)
現地の文化を学び、人と人で信頼を築く。アナログ手法も効果的
WOVN:
近鉄・都ホテルズさん、温故知新さんでも、インバウンド集客に効果があったと感じる取り組みがあれば、教えてください。
能川(近鉄・都ホテルズ):
アナログな手法も効果的だと考えています。OTA も活用していますが、ターゲットとしている国には当社のスタッフが現地を訪問し、できる限りその国の旅行会社とコミュニケーションを取るようにしています。そしてその国の文化や歴史を学び、持ち帰ってチェーンホテル全体で共有します。サービスや食事対応などに反映させることで、お客様にも「自分たちを理解してくれている」と感じていただき、結果的に集客効果を生むと考えています。
OTA でも、担当の方と人と人とのつながりが生まれると、更に予約へとつながることがありますので、アナログなコミュニケーションも大事にしています。
松山(温故知新):
当社のインバウンド集客は、これから伸ばしていく段階だと考えています。SNS を中心とした Web マーケティングの有効性は感じていて、予算配分を試行錯誤しています。当社はタイプの異なるホテルをいくつも展開しているため、全てをまとめて「温故知新グループは幅広く展開している」というブランドイメージを、各国でどう構築していくかが課題です。
富裕層の方は日本を旅行される際、旅をアレンジするブティック型のエージェントやコンシェルジュなどを利用することが多いです。こうしたエージェントとの関係構築は王道ですが、その層も含めて Web マーケティングの対象だと考えています。「このホテルを選んでおけば安心だ」と思ってもらえるような、信頼感を高めることが極めて重要です。

(温故知新 松山 氏)
その土地や宿ならではの体験価値、文化をストーリーと共に伝える
WOVN:
次に、外国人旅行者が関心を持つポイントや、効果的な情報発信のあり方についてお伺いします。松山さんは、特に地方への誘客を進めるうえで、どのような情報発信の戦略を意識されていますか?
松山(温故知新):
最近の訪日外国人の方の中には、東京や京都といった観光都市だけでなく、地方を訪れる方が増えています。その背景には、国際都市化が進んだ大都市よりも、地方にこそ“日本らしさ”や“本来の文化・風景”が残っているという認識が広がっていることがあります。だからこそ、地方を「日本らしさをより体験できる場所」として、どのようにストーリー仕立てで伝えていくかが重要です。
具体的な戦略としては、「クラフトツーリズム」をインバウンド向けに広げたいと考えています。例えば、職人の町・富山県高岡市では、工場見学や職人との対話を通じて、ものづくりの現場を体験してもらう。職人の想いや技を知ることで、製品に対する見方が変わり、ときには高付加価値な製品の購入につながる。そんな流れを生み出したいと考えています。
WOVN:
地域ごとの個性を、ストーリー仕立てにして体験とセットで打ち出していくということですね。
一方で、Nazuna さんは「おせっかい」という価値を提供されていますが、その魅力をどのように発信していますか。
渡邊(Nazuna):
「おせっかいな宿」として知ってもらうことよりも、実際に訪れて「おせっかい」を体験していただくことで、心を動かされるお客様が非常に多いと感じています。宿泊施設としての設備やサービス内容は情報発信しやすい一方で、「おせっかい」という価値は、滞在中にスタッフとの交流を通じて「日本人らしさや温かさ」の中から感じていただくのが何よりも大切です。
私たちの温かさが伝わっているからこそ、接客したスタッフ宛にお客様から感謝の手紙をいただくこともあります。
一方で、「旅マエ・旅ナカ・旅アト」という3軸のうち、旅ナカでしか「おせっかい」を提供できないという課題もあります。今後は、旅マエや旅アトにも体験を提供することで、お客様の満足度を高められるかを模索していきたいと考えています。
WOVN:
能川さんは、志摩観光ホテルのような地方の施設に人を呼ぶために、どのような発信が効果的だとお考えですか。
能川(近鉄・都ホテルズ):
都市部のホテルはアクセスの良さなどの機能的価値を提供し、地方のホテルはその土地ならではの体験を通じて情緒的価値を提供すべきだと考えています。志摩観光ホテルでは、料理を目的に訪れる方が多く、昨年文化庁長官賞を受賞した総料理長の樋口 宏江は「たとえ気候変動によってその土地の食材が手に入らなくなっても、その土地の食文化がなくなるということではない。受け継がれてきた食材の目利きや調理方法などそれ自体が文化であり、文化は料理に宿る」と話しています。こうしたストーリーと共に文化を伝えることが重要です。志摩観光ホテルでも、さらに力を入れて取り組んでいきたいと考えています。

(近鉄・都ホテルズ 能川 氏)
国によって価値の感じ方は異なる。顧客理解と伝えるメッセージを大切に
WOVN:
文化や体験、ストーリーの重要性について伺いましたが、このような価値を外国人に効果的に伝えるためには、どのような工夫が必要だとお考えですか。
渡邊(Nazuna):
文化やストーリーに対する価値の感じ方は、インバウンドと日本人では大きく異なると感じています。例えば、日本人のお客様にとっては1万円程度で体験できるお茶の体験が、海外のお客様にとっては400万円を支払ってでも参加したい特別な体験として受け止められることがあります。何に価値を感じるか、その違いを意識して伝えていかなければならないですね。
WOVN:
最後に、外国の方に日本を訪れたいと思っていただくために大切なこと、そして今後の展望をお聞かせください。
松山(温故知新):
今後、日本全体でインバウンド6,000万人を目指す中で、地方空港がインバウンドを受け入れることが必須です。地方にこそ、日本人の私たちでさえ知らない「日本の魅力」が溢れています。それをいかに伝えていくかが、これから問われていくと思います。
渡邊(Nazuna):
SNS が加速する中、ストーリーや歴史、その土地にどんな背景があり、どんな人々が暮らしているのかを丁寧に伝えることが、インバウンドのお客様に価値を感じていただくために不可欠です。未来だけでなく、過去の歴史を遡ってメッセージを伝えていくことが、これからの発信の鍵になると思います。
能川(近鉄・都ホテルズ):
顧客理解が重要だと考えています。例えば、欧米の方は文化体験を好みますが、東南アジアの方はコストパフォーマンスを重視し、中東の方は食事への配慮を求めるなど、国や地域によって期待するものが異なります。どの国の方に来ていただきたいかを明確にし、それに合わせて内容を工夫し、しっかりと伝えていくことが重要だと考えています。

Web サイト多言語化のご相談は WOVN へ
Wovn Technologies株式会社は Web サイト多言語化ソリューション「WOVN.io」を提供しています。多言語化についてご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードください。

WOVN マーケティング編集部
WOVN マーケティング編集部は、企業の海外展開やインバウンド対応、外国人従業員対応などに役立つ情報を発信します。グローバルビジネスがテーマの大規模カンファレンスやセミナーも開催しています。 有識者インタビューやイベントレポートなどをはじめ、企業の海外戦略・外国人対応を成功に導く Multilingual Experience(MX=多言語体験)に関する様々な情報をお届けします。
Related posts

買い物は「体験」を超える─インバウンド消費の未来を拓く小売3社の挑戦─|三越伊勢丹 額田氏・セブン-イレブン 吉村氏・コメ兵 甲斐氏|GLOBALIZED インバウンド

コロナ禍で見出した、インバウンド復活へ繋ぐ東京タワーの取り組み|TOKYO TOWER 髙尾氏 | GLOBALIZED インバウンド2.0

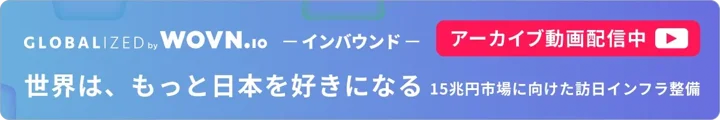








.webp)




